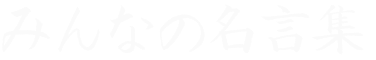戦わずして勝ちを得るのは、良将の成すところである。
鳴かぬなら、鳴かせてみせようホトトギス。
人と物争うべからず、人に心をゆるすべからず。
この黄金の輝きも 茶の一服に勝るものかな
ひそかにわが身の目付に頼みおき、時々異見を承わり、わが身の善悪を聞きて、万事に心を付けること、将たる者、第一の要務なり。
金を貯め込むのは良き士を牢に押し込むに等しい
いつも前に出ることがよい。そして戦のときでも先駆けるのだ。
人の意見を聞いてから出る知恵は、本当の知恵ではない
一歩一歩、着実に積み重ねていけば、予想以上の結果が得られる
猿・日吉丸・藤吉郎・秀吉・大閤、これもまた皆が嫌がるところでの我慢があったればこそ
戦は六、七分の勝ちを十分とする。
主従や友達の間が不和になるのは、わがままが原因だ。
降参した者は、それ以上責めてはいけない
敵の逃げ道を作っておいてから攻めよ
いくら謙信や信玄が名将でも、俺には敵わない。彼らは早く死んでよかったのだ。生きていれば、必ず俺の部下になっていただろう。
主人は無理を言うなる者と知れ
信長公は勇将なり 良将にあらず
何事もつくづくと思い出すべきではない
やるべき事が明確であるからこそ、日夜、寝食忘れて没頭できる。
世が安らかになるのであれば、わしはいくらでも金を使う
負けると思えば負ける、勝つと思えば勝つ。逆になろうと、人には勝つと言い聞かすべし。
露と落ち露と消えにし我が身かな 浪花の事は夢のまた夢
夢は大きいほど良いと言うが、わしはすぐ手の届くことを言っている